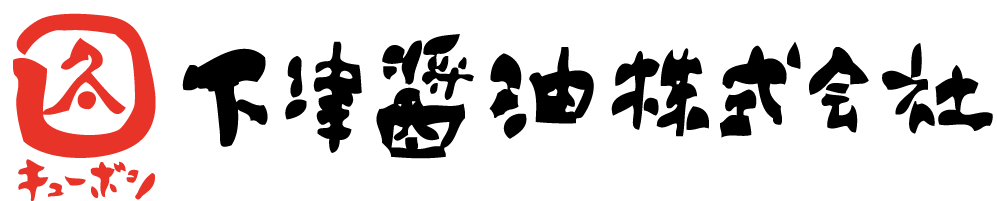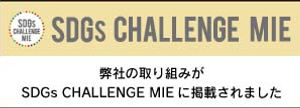下津醤油について

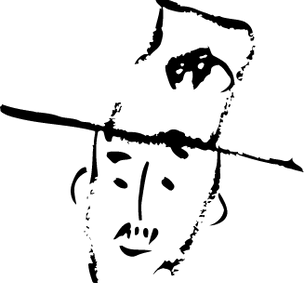
会社概要
会社名 下津醤油株式会社
所在地 三重県津市一身田町362番地
電 話 059-232-2121(代)
FAX 059-231-2800
代表取締役社長 下津浩嗣
取締役会長 下津和文
創 業 安政3年(1856年)
設 立 大正7年(1918年)6月25日
資本金 1,000万円
目 的 1.醤油の製造 2.各種調味料の製造 3.各種たれ類の製造 4.前各号に付帯する一切の業務
決算期 8月
主要取引先 山忠食品工業(株)/日清製粉(株)/ヤマモリ(株)/東海コープ事業連合/ 三重県醤油味噌工業(協)/
伊賀の里モクモク手作りファーム/(株)三重研醸社/マルキ商店
主要取引銀行 百五銀行 一身田支店 / 三十三銀行一身田支店
経営理念
企業規模のみを追わず、健全経営により社会に信頼され、
存在感のあるキラリと輝く企業を目指します。
経営理念補足説明
下津醤油版「キラリと輝く企業 5つの“こと”」
-
下津醤油で働いているスタッフやその家族に「下津醤油って良い働き場やん♪」って思ってもらえること。
-
地域の人々から「下津醤油があって誇りに思うわ~」って感じてもらえること。
-
下津醤油製品を使っている人々や下津醤油と取引している企業に「下津醤油が無いと困る~」って思ってもらえること。
-
スタッフを中心として、常に挑戦し続けた結果がメディア等に紹介されて「下津醤油って頑張ってるよね~」とちょっとした噂になること。
-
下津醤油に来社される人々に「下津醤油ってええ会社やな~」って思ってもらえること。
ISO22000 「食品安全方針」
1. 下津醤油の一人ひとりがお客様の立場に立ち、誠実かつ前向きに行動します
2. 各部門において年度目標を設定し、部門長を中心として達成を目指します
3. 設備の充実及び社員教育に努め、お客様が安心出来る製造環境を整えます
4. 技術の伝承と研鑽に努め、お客様にご満足頂ける製品の開発を目指します
5. お客様に安心を届けられるよう、法令を遵守し社内外の情報共有に努めます
写真家の浅田政志さんに下津醤油の人々を撮影していただきました。
(特別出演・・野田米菓の女将と金鍋の女将)

沿革
1856(安政3年)一身田で醤油・味噌の製造を始める
1918(大正7年6月)下津醤油株式会社 設立。資本金10万円。下津利兵衛、代表取締役社長に就任
1925(大正14年11月)資本金30万円に増資。現在地に移動
1939(昭和14年1月)下津謙蔵、代表取締役社長に就任
1947(昭和22年1月)堀久八、代表取締役社長に就任
1948(昭和23年6月)資本金50万円に増資
1951(昭和26年1月)下津泰蔵、代表取締役社長に就任
1953(昭和28年12月)資本金150万円に増資
1958(昭和33年8月)台風7号により工場が浸水、被害甚大
1959(昭和34年9月)台風15号(伊勢湾台風)により直接・間接の被害甚大
1970(昭和45年1月)津醤油味噌製造協同組合 設立
1974(昭和49年7月)大雨による志登茂川の氾濫で工場浸水、被害甚大
1975(昭和50年1月)下津和文、代表取締役社長に就任
1975(昭和50年6月)屋外醗酵タンク20kl×4 完成
1988(昭和63年10月)原料処理・麹室棟・第1作業場、屋外醗酵タンク50kl×5 完成
1990(平成2年10月)屋外醗酵タンク36kl×4 完成
1991(平成3年1月)圧搾棟 完成
1992(平成4年10月)資本金600万円に増資
1993(平成5年7月)伊勢醤油本舗株式会社へ出資
1993(平成5年10月)資本金1,000万円に増資
1993(平成5年11月)屋外醗酵タンク36kl×4 完成
2000(平成12年11月)第2作業棟、ろ過・冷蔵庫棟 完成
2003(平成15年10月)特級醤油が第32回全国醬油品評会に於いて農林水産省総合食料局長賞を受賞
2004(平成16年5月)下津醤油株式会社・津醤油味噌製造協業組合が品質マネジメントシステムISO9001を認証取得
2004(平成16年10月)事務所 増築
2008(平成20年3月)津醤油味噌製造協業組合 解散
2009(平成21年10月)下津和文、代表取締役会長に就任 下津浩嗣、代表取締役社長に就任
2012(平成24年1月)塩水溶解場 完成
2012(平成24年3月)第1作業場・第2作業場 改修
2012(平成24年10月)特級醤油が第40回全国醤油品評会に於いて農林水産大臣賞を受賞
2012(平成24年12月)生揚冷蔵庫増設
2013(平成25年2月)フィルム充填機(5㎖~50㎖)導入
2013(平成25年4月)株式会社あかり屋へ出資
2016(平成28年5月)食品安全マネジメントシステムISO22000を認証取得
2016(平成28年11月)諸味自動充填装置導入
2017(平成29年10月)特級醤油利兵衛が第45回全国醤油品評会に於いて農林水産省食料産業局長賞を受賞
2018(平成30年10月)特級醤油利兵衛が第46回全国醤油品評会に於いて農林水産大臣賞を受賞
2019(令和元年10月)特級醤油利兵衛が第47回全国醤油品評会に於いて農林水産大臣を受賞
2020(令和2年10月)下津醤油の直売所を工場前へ移転
2021(令和3年10月)特級醤油利兵衛が第48回全国醤油品評会に於いて農林水産大臣官房長賞を受賞
2021(令和3年10月)下津和文、取締役会長に就任
2022(令和4年11月)工場改装、フィルム充填機(50㎖~1000㎖)導入
2023(令和6年8月)醸造調味液専用自動圧搾機導入
全国醤油品評会
醤油の品質向上と表示の適正化を図り、消費者に良質の醤油を提供し、合わせて業界の発展に寄与することを目的として、日本農林規格(JAS)が整った昭和48年より毎年開催されています。全国の醤油メーカーが出品をし、審査を経て農林水産大臣賞、食料産業局長賞、優秀賞が決定されます。全国醤油品評会の制度は平成17年に大幅改正され、これまでは参考品であった大手5社の製品も対象になり、審査が行われるようになりました。下津醤油では同品評会においてこれまで数々の賞を受賞し、最優秀賞である農林水産大臣賞3度に渡って受賞しています。
平成15年 農林水産省総合食料局長賞
平成17年 優秀賞
平成18年 優秀賞
平成19年 優秀賞
平成21年 優秀賞
平成24年 農林水産大臣賞
平成26年 優秀賞
平成29年 農林水産省食料産業局長賞
平成30年 農林水産大臣賞
令和元年 農林水産大臣賞
令和3年 農林水産大臣官房長賞
社長挨拶

全国には、今でも1,100を超える醤油製造会社が在ります。大手5社で50%、中堅会社を含めた上位15社で出荷量の75%を占めるような業界です。それでも多くの蔵がまだ残っているのは、それぞれの蔵が様々な工夫を繰り返し、挑戦し続けているからだと思います。
当社は経営理念を「規模のみを追わず、健全経営により社会に信頼され、存在感のあるキラリと輝く企業を目指す」と定め、常に激動する時代の中で、お客様に必要とされ続けるために製造環境の改善や様々な新商品開発、ソフト面のバージョンアップなど様々なことに挑戦・改善を繰り返してきました。
それらを支えるのは、当社の社員とすべての関係者です。また地域の方々の温かい応援が本当にありがたいです。
これからも、小さな醤油屋はキラリと輝けるように、常に夢を持ち挑戦し続けます。
代表取締役 下津 浩嗣
SDGs活動


下津醤油株式会社のSDGs宣言
当社は国連が推奨する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、経営理念にある「キラリと輝く企業」を実現するための活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

①醤油を年間に約600,000リットル製造する中で、醤油粕 約75,000kg、醤油油 約7,000リットルが排出されます。現在、醤油粕は地元あのつ牧場さんの乳牛の飼料に、醤油油は引き取られ、工業用油脂製品の基礎原料として再利用されています。
②同じ一身田町内の高田本山敷地内高田会館 和彩akariでは、三重郡多気町で手間暇かけて作られるゴツゴツした伊勢芋を利用して、名物 伊勢芋とろろを提供しています。
伊勢芋は皮を剥くのも結構大変なのですが、農家さんも形の悪い伊勢芋は皮を剥いて出荷していました。大切に育てられた伊勢芋を全て使いたい想いから、当社は農家さんに伊勢芋の皮をしっかりと処理していただき購入して、伊勢芋の皮の粉末を作り、三重県の原料を積極的に使用した、伊勢芋かりんとうを開発しました。
当社で全て手作りした伊勢芋かりんとうは現在5種類の味で販売しており、お客様にも好評です。





①醤油を製造する中で、地域の小学生を中心に「醤油博士」として出前授業をすると共に、工場見学の受け入れも実施しています。夏休みや工場感謝祭の際も工場見学会を実施しています。
醤油を作る楽しさや大変さ、伝統を守る大切さを地域で発信する事は製造者としてとても大切だと考えています。

①工場敷地や直売所前の防犯カメラが、地域のお役立ちに繋がっています。
②平成24年に一身田商工振興会のメンバーが出資しあい、設立された高田会館・ぼんぼりを運営する株式会社あかり屋の筆頭株主として、代表取締役を務めると共に、地域の活性化の一助となるよう、取り組んでおります。
③一身田商工振興会のメンバーとして、イベントを中心に共に活動を行うことで、地域活性化に努めております。



①丸大豆醤油については、地元三重県産の大豆と小麦を使用しています。
②商品開発は可能な限り地域の作物を活用する事により、輸送に係る燃料の削減や地域活性化に繋がっています。
③取引企業様や地域の様々な会とはパートナーとして、それぞれの経験も活かし、共に持続可能な社会を作り上げます。

当社は三重県SDGs推進パートナーに登録されました
今後、弊社の活動についてさらに詳しくホームページ等で発信させていただきながら、積極的に活動を推進していきます。
バナーのリンク先はパート①です
パート2
https://www.youtube.com/watch?v=MTknywDOC2c
パート③
https://www.youtube.com/watch?v=VJQOQuwdD-w
パート④

久星のいわれ
下津醤油の創業者下津利兵衛は文久元年から昭和13年まで江戸、明治、昭和と激動の時代を生き抜いた、気骨ある事業家でした。三重県関の田中家から姉が下津家に嫁ぎ、子供が出来なかった事から、弟である4男の利兵衛を養子としました。利兵衛は事業家であると同時に、茶道をこよなく愛しました。茶道を学ぶことは、茶道の作法を学ぶという手段を経て、日本の思想、道徳、宗教、美術、文芸、建築、音楽、味覚等、あらゆる文化の総合に触れるということでありました。利兵衛は茶人である久太夫と食通である魯山人、2人の大物の名前を商号に使いたいと思ったようで、それは利兵衛の生き様から推察できます。
久太夫との接点は10代目の時、下津家の次女が川喜田家の分家久三郎に嫁いでいることや、お茶に招き、夫人や令嬢が当家を訪れ、その時の様子が絵入り礼状として残されています。利兵衛が魯山人の作った星が丘茶寮(東京)へ足を運び、その時の様子は利兵衛の旅日記に残されています。利兵衛はお茶を楽しむため、大正9年から3年かけて別荘を造り珂雪園と名付けました。珂雪園とは雪のように真っ白な貝という意味で利兵衛の生き様が出ています。
伊勢銀行が破綻した際、利兵衛はお客様に迷惑はかけられないと、私財を投げ打ったことがエピソードとして利兵衛が死亡した際の新聞に載っています。所得調査員に選ばれたことを誇りにしていた利兵衛は、会社の利益より、川喜田久太夫や北大路魯山人に美味しいといわれる醤油作りを目標にするため、敢えて大物2人の名前を商号に使うことで、自分を奮いたたせていたのではないでしょうか。こればかりはあの世に行って、本人に聞いてみないとわかりません。